vespa50s1978 2011/12/24 by KBの遠藤
昨日作業完了!となったvespa50s
 これ、1978年位に製造されたベスパで、この辺になると色々と後の50sと違いはあるんだけど、この年式前後のベスパで厄介なのが、リアブレーキペダルを外す作業。
これ、1978年位に製造されたベスパで、この辺になると色々と後の50sと違いはあるんだけど、この年式前後のベスパで厄介なのが、リアブレーキペダルを外す作業。
ブレーキペダルが生えてるとこの穴は、丸。
っで、ブレーキペダルは四角。
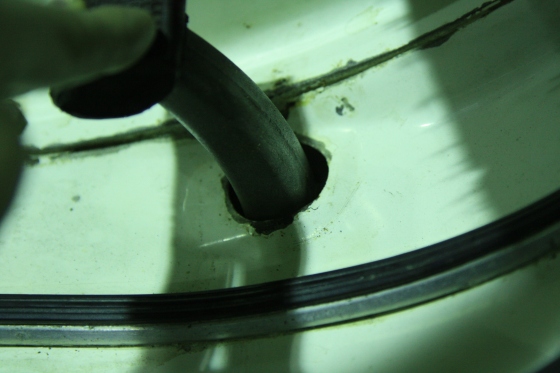 ↑の写真、チョッと分かり辛いけど。
↑の写真、チョッと分かり辛いけど。
よく、再生産前、再生産後を見分ける時に、ブレーキの穴が丸いか四角いか。なんて話が出てきますよね。
丸穴&四角ペダルでも、この組み合わせの後期の方はブレーキペダル分解は特に困りませんが、初期の、リアブレーキケーブルが両切りタイプの車体だと、すんなり外す事が出来る時もあるけど、大半のパターンは、こんなのどうやってバラスすんだよ・・・
ってな状態になります。
自分こんな時、車体にペダルをはめたまま分解していってしまいます。
 こんな感じに。
こんな感じに。
ここまでの状況、詳しく説明するのは、無理。
やった事ある人にしか通じないですね。
っが、今回は、
 ペダルのシャフトがガッツリと錆び付いていた為、更に苦労させられました。。。。
ペダルのシャフトがガッツリと錆び付いていた為、更に苦労させられました。。。。
2日くらい、油に漬け置いてやっと分解出来ました。
何故、こんな事しなければいけないのかというと、全ての元凶は
 右側に移るケーブルの留め具。
右側に移るケーブルの留め具。
アイツが引っかかるから、すんなり取れないんですよ。
故に、留め具を先に外してしまったりしながらボディーに付けたまま分解していくんです。
組む時は当然、ループタイプの、写真に組み込んであるタイプのケーブルに組み替えました。
この年式だと、
 ストップランプスイッチも違うし、ブレーキペダルを固定している3本のボルトの内、ぼでぃーの下から締め込むボルトには
ストップランプスイッチも違うし、ブレーキペダルを固定している3本のボルトの内、ぼでぃーの下から締め込むボルトには
 タブワッシャーが使われています。
タブワッシャーが使われています。
その他の違いは
 フライホイールが、プラーを使用しなくて外せるタイプの物が付いてます。
フライホイールが、プラーを使用しなくて外せるタイプの物が付いてます。
っが、これ、いけてないんですよ。
よって、サービスで、後のモデルに使用される、プーラーを使うタイプのフライホイールに交換しちゃいました。
サービス、というより、次回ばらす時に苦労しないように交換しただけ。
作業者側の視点で交換しちゃったパーツです。
ジャンクションボックスの配線も
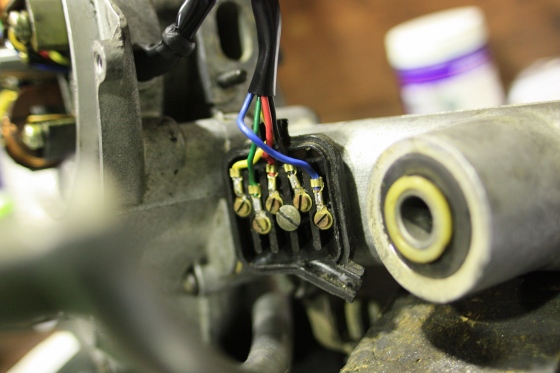 旧型のビス留めタイプ。
旧型のビス留めタイプ。
ケーブルステー、クラッチカバーは、後のモデルと共通の物です。
ホイールを留めるホイールクリップボルトも、
 後のモデルに付くボルトとは頭のデザインが違います。
後のモデルに付くボルトとは頭のデザインが違います。
これのちょっと前は、FIATの刻印入りなんてのもありました。
久しぶりに、誰の役にも立たない、誰も興味がないと思われるベスパネタを、真面目に書いちゃった2011年12月24日。
クリスマスイブの夜。
自分、あと少ししたら、まさか!!!な感じで、クリスマスパーリーに紛れ込ませて頂き酒などグビッと飲んでこようかと。
自ら参加するのは、生まれて初めて(笑)
端っこで、小さな態度で、限りなく気配というものを消して、酒飲んで帰ってきます。
そんな理由で、そろそろ閉店。
サヨナラ

ブレーキペダルが生えてるとこの穴は、丸。
っで、ブレーキペダルは四角。
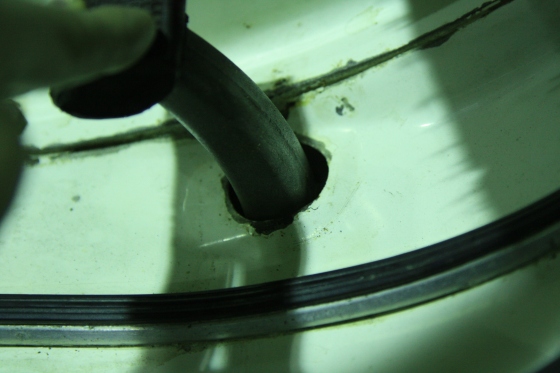
よく、再生産前、再生産後を見分ける時に、ブレーキの穴が丸いか四角いか。なんて話が出てきますよね。
丸穴&四角ペダルでも、この組み合わせの後期の方はブレーキペダル分解は特に困りませんが、初期の、リアブレーキケーブルが両切りタイプの車体だと、すんなり外す事が出来る時もあるけど、大半のパターンは、こんなのどうやってバラスすんだよ・・・
ってな状態になります。
自分こんな時、車体にペダルをはめたまま分解していってしまいます。

ここまでの状況、詳しく説明するのは、無理。
やった事ある人にしか通じないですね。
っが、今回は、

2日くらい、油に漬け置いてやっと分解出来ました。
何故、こんな事しなければいけないのかというと、全ての元凶は

アイツが引っかかるから、すんなり取れないんですよ。
故に、留め具を先に外してしまったりしながらボディーに付けたまま分解していくんです。
組む時は当然、ループタイプの、写真に組み込んであるタイプのケーブルに組み替えました。
この年式だと、


その他の違いは

っが、これ、いけてないんですよ。
よって、サービスで、後のモデルに使用される、プーラーを使うタイプのフライホイールに交換しちゃいました。
サービス、というより、次回ばらす時に苦労しないように交換しただけ。
作業者側の視点で交換しちゃったパーツです。
ジャンクションボックスの配線も
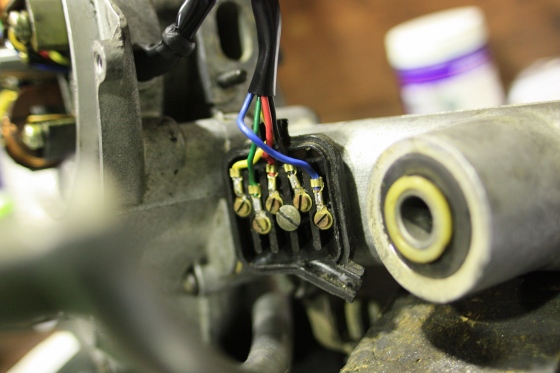
ケーブルステー、クラッチカバーは、後のモデルと共通の物です。
ホイールを留めるホイールクリップボルトも、

これのちょっと前は、FIATの刻印入りなんてのもありました。
久しぶりに、誰の役にも立たない、誰も興味がないと思われるベスパネタを、真面目に書いちゃった2011年12月24日。
クリスマスイブの夜。
自分、あと少ししたら、まさか!!!な感じで、クリスマスパーリーに紛れ込ませて頂き酒などグビッと飲んでこようかと。
自ら参加するのは、生まれて初めて(笑)
端っこで、小さな態度で、限りなく気配というものを消して、酒飲んで帰ってきます。
そんな理由で、そろそろ閉店。
サヨナラ


